
大府市S・E氏提供
法 話
(143)
|
|
 大府市S・E氏提供 |
| |
1月16日アルジェリアで人質事件が発生。アルカイダ系の武装集団が襲撃し、(株)日揮の日本人社員17名を人質に。早い時点で3名の生存が判明。その後4名生存が確認された一方、10人の死亡が判明。1月25日、9人の犠牲者が政府専用機で帰国。翌26日には1人の遺体が民間機で日本へ搬送され、現地へ赴いていた(株)日揮関係者と政府要人も帰国。犠牲になられた関係者には心より哀悼の意を表したいと思います。
事件発生地イナメナスはアルジェリアの首都アルジェからは遠隔地(ほぼ東京-博多と同じ)ということもあり、加えてアルジェリア政府の報道管制等もあって、当初は事件の全容がなかなか掴めず情報が錯綜しました。(株)日揮の天然ガス精製プラントをイスラム過激派が襲撃し、日本人をはじめ多人数を人質にとったわけですが、目的は精製施設の破壊というよりは、人質を国外へ連れ出し、それを盾にして要求を突きつけることがむしろ目的であったように思われます。
因みに、イスラム(マホメット)教とはどんな宗教なのでしょう。世界の三大宗教について主要項目を比較対照してみました。ある統計によれば、それぞれの信仰人口はキリスト教:20億人、イスラム教:13億人、仏教:3億5千万人とのこと。仏教については、当山の宗派である浄土真宗とそれ以外の宗派を分けて比較してみました。
|
神・本尊 |
開祖・救世主 |
聖 典 |
開宗時代 |
礼拝対象 |
|
|
イスラム教 |
アッラー |
マホメット |
コーラン |
西暦7世紀 |
(無)メッカの方角 |
|
キリスト教 |
キリスト |
イエス |
聖書 |
西暦1世紀 |
キリスト像 |
|
浄土真宗 |
阿弥陀如来 |
親鸞聖人 |
浄土三部経 |
西暦12世紀 |
阿弥陀如来 |
|
仏教各宗派 |
諸仏・菩薩 |
各宗祖・釈尊 |
諸経典 |
西暦前5世紀 |
諸仏・菩薩 |
アルジェリアはイスラム教国、イスラム教が国教になっています。国民の50%以上がイスラム教徒の国は世界で約50か国あるといわれています。私自身がかつて訪問したことのあるイスラム国家はトルコ、インドネシア、マレーシア。イスラム国家と言っても、詳しいことは分かりませんが、国々によって信奉する教義内容や儀式作法も多少違うのでしょう。
宗教的生活習慣も多少緩慢の差があるようです。例えば、女性は肌を他人に見せないようにということで、ブルカやチャドルを着用することになっているようです。アフガニスタンで着用されているブルカなどは全身を完全に覆った上に、眼の部分が細かい網状になっていて、内部からは外が見えるが、外からは内部は全く見えないとのこと。一方、インドネシアなどでは洋装にスカーフだけのコスチュームも許されているようです。
イスラム教では宗教シンボルの絵像や彫像を礼拝対象としません。モスクの壁の窪み(ミラーブ)を通してメッカのカーバ神殿に向かって礼拝するとのこと。先日、イスラム教徒の従業員が働く日本企業内にも、メッカの方角に向かって礼拝できる礼拝室を設えたとのTV報道もありました。礼拝は1日5回、朝・昼・夕方・夜・就寝前。なお、礼拝の前には必ず手足を洗わなければならないとのこと。日本流では“手水を使う”ということになりましょうか。
ところで、イスラム教徒の食事はといえば、一般的によく知られていることですが、豚肉を食することは禁じられています。トンカツを揚げた油でエビフライをつくることもダメ。かつて私が主宰する団体がインドネシアからガムラン楽団を招いて名古屋で演奏会を開いたことがありました。リハーサルのあとレストランで昼食をとることになり、店頭のメニュー・サンプルを前にしてひとしきり議論。トンカツはダメだとか、このカレーには豚肉は入っていますかとか、これは何のスープですかと議論百出。シェフまで呼び出して素材の確認をしたことを思い出します。魚はOKですが、鳥や牛はト殺の仕方によってはダメのケースがある模様。
世界の歴史の中で幾たびか宗教戦争がありました。ユダヤ教対イスラム教、キリスト教対イスラム教、カソリック対プロテスタント等々。トルコはイスタンブール、アヤソフィアのドーム天井にはキリスト教聖母子のモザイク画があります。戦争に負けてキリスト教の教会がイスラム教のモスクに転用され、ドーム天井のキリスト教聖母子のモザイク画は漆喰で塗りつぶされたのですが、漆喰がはがれてキリスト教の絵が現れたとのこと。宗教戦争の典型的な遺産?といえるのかも。
世界の宗教戦争に比べれば小競り合い程度でしょうが、日本国内でも教団間の衝突はありました。例えば、一向宗(真宗)門徒対戦国大名、一向宗対法華宗(日蓮宗)etc。仏陀誕生から、他2大宗教の開祖誕生を踏まえ、奈良・平安・鎌倉仏教の流れをグラフ上に整理してみました。現在大方の一般家庭で信奉されている仏教の淵源は、ほぼこの鎌倉時代の法然、親鸞、道元、日蓮の四祖師開宗の四宗各派に求められます。
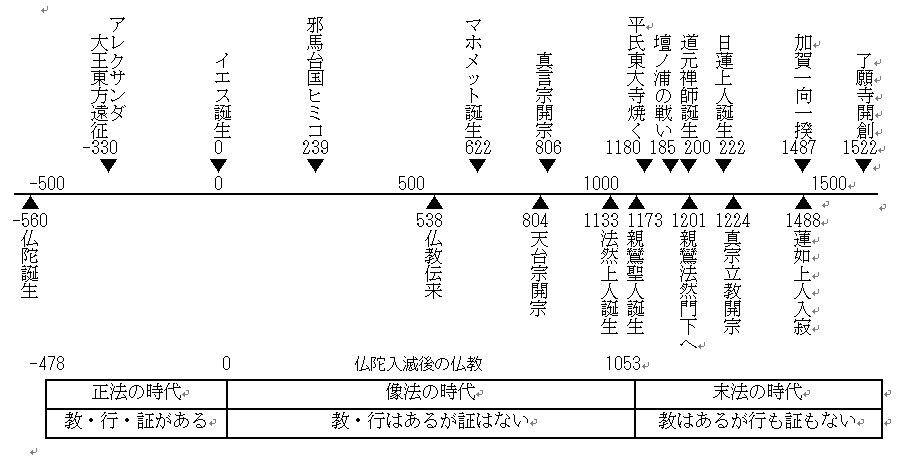
1053年末法の時代到来ということで、藤原道長が宇治・平等院に鳳凰堂を建立(世界遺産・現在修復中)。浄土教信仰が一般大衆に一気に広がりをみせると同時に、道元禅師の禅による救い、日蓮上人の法華信仰も在家の人々に浸透。貴族仏教から在家仏教へ。日本仏教史の中で鎌倉時代は実に大きなエポック・メイキングの時代といってもよろしいのではないでしょうか。
合掌
《2013.2.3 前住職・本田眞哉・記》